預貯金口座付番制度で相続が楽になる?手続きの流れや注意点など解説します
画面を横向きにすると見やすくなります。
預貯金口座付番制度って、知っていますか?

お金にかかわる国の制度に、
「預貯金口座付番制度」
というものがあるのですが、
この制度をご存じの方、
いらっしゃいますか?
ご存じでない方も多いかと思います。
それもそのはず、この制度は、2018年1月に始まった新しい制度で、
利用者がまだ少なく、認知度も低いのが現状です。
しかし、2025年4月1日以降、関連法令の施行によりこの制度の機能が強化され、
それにより、相続手続きにも一定の恩恵が受けられる可能性が出てきました。
相続手続きとの関わり、及び注意点を中心に解説していきます。
預貯金口座付番制度とは
預貯金口座付番制度は、国が進めるマイナンバー活用策の一つです。
口座管理法という法律に基づいて運用されています。
具体的には、口座を持つ金融機関にマイナンバーを届け出て、
口座とマイナンバーを紐付けることにより、
相続手続きなどの際、一つの金融機関の窓口に申し出ることで、
マイナンバーが付番されたすべての預貯金口座を把握できるようになる、というものです。
公金受取口座とは異なります
なお、同じくマイナンバーと預貯金口座を紐付ける国の制度として、
「公金受取口座登録制度」というものがあります。
こちらも、金融機関にマイナンバーを届け出るという意味では同じなのですが、
制度の趣旨が「国から給付金等を支給する際、申込などの手続きをすることなく、
登録している口座に、速やかに給付金等を支払うための制度」となっており、
預貯金口座付番制度とは別個の制度となっています。
預貯金口座付番制度の仕組み
預貯金口座付番制度は当初、預金者本人のマイナンバーと、
マイナンバーの届出を受けた金融機関にある本人の口座のみを紐付ける仕組みでした。
しかし、2025年4月1日以降、この仕組みが大きく変わりました。
具体的には、金融機関に預貯金口座を持つ人が、
- マイナポータル
- 利用している金融機関のうち、任意の1つの金融機関
のいずれかで、制度利用の申請をすると、マイナンバーの情報が、
預金保険機構という、国の機関に伝えられます。
すると、預金保険機構の方で、すべての金融機関に口座開設状況を照会し、
申請者が有するすべての金融機関の口座に、マイナンバーを紐付けてくれるのです。
このような仕組みに変わったことで、
金融機関ごとに紐付けの手続きを行う必要がなくなりました。
また、海外に移住し、日本の住民登録を抹消した場合は、制度開始当初と同様、
申し出をした金融機関の口座のみ紐付け対象となります。
一部、手続きの対象外となる金融機関もあります
なお、デジタル庁によると、日本国内に支店を持つ外国の金融機関や、
組合系金融機関など、一部の金融機関では、この制度に基づく、
- 他の金融機関やマイナポータルから、自行口座とマイナンバーを紐付ける手続き
- 相続手続きの際などに、口座に関する情報の提供を受ける
- 相続手続きの際などに、口座に関する情報の提供に係る照会を受け付ける
この制度は、相続手続きとどのように関係する?
と、ここまで見ると、一見、
預貯金口座付番制度と相続手続きには関係性がなさそうに見えます。
しかし、そこも2025年4月1日以降の仕組み変更で関係するようになりました。
仕組みの変更により、亡くなられた方(被相続人)が生前、
預貯金口座付番制度を利用していた場合、その相続人は、
亡くなられた方が口座を持っていた金融機関のうち、任意の1つの金融機関に、
死亡の連絡と同時に「相続時口座照会」を依頼できるようになります。
すると、依頼を受けた金融機関が預金保険機構に調査を委託、
預金保険機構が、他の金融機関に亡くなられた方名義の預貯金口座があるかどうか、
付番されたマイナンバーによって調査を行い、
その結果を後日、相続人に郵送で伝えてくれるのです。
これにより、亡くなられた方名義の口座を把握しやすくなりました。
なお、相続人には「包括受遺者」を含みます。
例えば、亡くなられた方が遺言書で、
「遺産はすべて財団法人に遺贈(寄付)する」と書いていた場合、
指名された財団法人は法律上、包括受遺者として、相続人と同じ立場になります。
そのため、当該財団法人も「相続時口座照会」ができる、という形です。
預貯金口座付番制度に基づく手続きを行うケースが、今後は出てくると考えられます。
相続手続きにおける預貯金口座付番制度のメリット
相続手続きにおいてどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
「自分の死後に備えたい方」と「亡くなられた方の相続人」、
それぞれの立場で見ていきますと、以下の通りとなります。
①自分の死後に備えたい方のメリット
自分の死後に備えるという意味では、
- 自己名義の預貯金口座を、もれなく相続してもらえる
という点がメリットになります。
預貯金口座をどれだけ持っているかは、人によって異なると思いますが、例えば、
- たくさんの金融機関に口座を持っており(概ね3金融機関以上)、
自分でもどの金融機関に口座を持っているか、分からなくなりつつある - ネット銀行など、預貯金通帳その他客観的に、
その金融機関に口座を持っていることがわかるものがない預貯金口座がある - ご自身が亡くなった際、相続人となるご家族とは別居しており、
どの金融機関に口座を持っているのか、あらかじめ伝えていない
預金保険機構にすべての自己名義の預貯金口座を紐付けてもらうことで、
ご自身が亡くなった際、ご家族が手続き漏れを起こすことなく、
すべての金融機関の口座について、相続手続きができるようになります。
②亡くなられた方の相続人のメリット
一方、亡くなられた方の相続人にとっては、
- 亡くなられた方が有していた預貯金口座を、一挙に把握できる
という点が大きなメリットだと言えます。
これまでは、亡くなられた方の遺品から預貯金通帳やキャッシュカードなどを探し、
どの金融機関に口座を持っていたのか、一つ一つ確認する必要がありました。
しかし近年では、ネット銀行など、その金融機関に口座を持っていることが、
視覚的・物的にわからないケースが増えつつあります。
そのため、預貯金口座の手続き漏れが生じてしまいやすくなっています。
万一、預貯金口座の手続き漏れがあると、
- 遺産分割協議のやり直しが必要になる可能性がある
- 相続税の申告・納税漏れにつながり、追徴課税の処分を受ける可能性がある
- 手続き漏れがきっかけで家族間の仲が悪くなってしまう可能性がある
など、面倒なだけでなく、心に大きなダメージを受けてしまう可能性がありました。
手続き漏れを起こさず、預貯金を相続できる可能性が高くなりました。
相続する側にとって、これはありがたいのではないでしょうか。
相続手続きにおける預貯金口座付番制度の注意点(デメリット)
先ほどはメリットを見てきましたが、
注意点(デメリット)にはどのようなものがあるでしょうか。
大きく分けると、以下の5つが挙げられます。
- ①あくまで任意であること
- ②一部、対応していない金融機関があること
- ③制度強化前の相続手続きには関係しない
- ④そこそこ高い手数料がかかる
- ⑤出入金ができなくなり、精算等が大変になる可能性がある
①あくまで任意であること
預貯金口座付番制度は、「任意」であるという大前提があります。
そのため、利用を希望する方が自ら金融機関に申し出て、
またはマイナポータルにて手続きをしない限り、この制度を利用することはできません。
国の方で勝手に預貯金口座とマイナンバーを紐付けることはないのです。
Bに預貯金口座付番制度を利用してもらいたいと考えていたとしても、
Bに利用する意思がない限り、この制度の利用はできないことをご理解下さい。
(決して無理強いしないで下さい。親子間の断絶につながる可能性がありますので…)
②一部、対応していない金融機関があること
先ほど概要を紹介した際に触れましたが、
2025年4月1日以降の預貯金口座付番制度に対応していない金融機関が一部存在します。
この制度を利用したいと思っても意味がない形になりますので、
紙の通帳を確実に手元に置いておくなど、ご自身が亡くなられた際、
ご家族にその口座の存在を知らせるための策を講じておく必要があります。
③制度強化前の相続手続きには関係しない
預貯金口座付番制度が相続手続きの場面で役に立つのは、あくまで、
2025年4月1日以降の制度強化後にマイナンバーと預貯金口座との紐付けを行った場合です。
2018年の預貯金口座付番制度開始以降、2025年3月31日までに行われた紐付けは、
あくまで「申し出をした金融機関に有する口座」のみが対象となっているため、
口座を有するすべての金融機関で個別に手続きをしていない限り、
紐付けがされている口座とされていない口座が混在している可能性があります。
例えば、2025年1月1日に亡くなられた場合、
亡くなられたのが2025年4月1日の制度強化よりも前ですので、
この制度によって有していた預貯金口座を把握することができず、
従来通り、預貯金通帳を探すなどして個別に口座の確認をする必要があります。
④そこそこ高い手数料がかかる
制度利用の申し出(マイナンバーを紐付けてもらう手続き)に費用はかかりません。
しかし、相続人が「相続時口座照会」を行う際には、手数料がかかります。
手数料は、預金保険機構の定めにより、5,060円(税込)です。
この金額は、どの金融機関で手続きを行った場合でも、
また、調査の結果、口座の有無が確認できなかった場合でも、同額となります。
金融機関に支払う手数料は、1金融機関あたり1,000円もかからないことが大半ですが、
この制度では、そこそこ高い手数料がかかることは覚えておくべきでしょう。
⑤出入金ができなくなり、精算等が大変になる可能性がある
相続時口座照会を申し込むと、預金保険機構において紐付けされている口座を確認し、
亡くなられた方名義の口座がある金融機関に、口座名義人が亡くなったことが伝えられます。
一般的に、金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを把握すると、
相続人からの申し出がなくても、当該口座の出入金を停止する措置を取ります。
そのため、預金保険機構からの通知がなされれば、金融機関の判断によって、
出入金が停止する可能性が高いと言えます。
そうなりますと、例えば、亡くなられた方が有していた金融機関の口座のうち、
A銀行の口座とB銀行の口座について、紙の預貯金通帳から存在がわかっていて、
A銀行に対して相続時口座照会の申し込みをした(この時点でA銀行の口座は出入金停止)後、
B銀行の口座から、葬儀や納骨などに必要なお金を下ろそうとすると、
B銀行の口座についても既に出入金停止の措置が取られていて、下ろせない…、
という事態が生じることが考えられます。
また、亡くなられた方が、その有する口座から、
ライフラインの利用料金など、定期的に口座から引き落とす設定をしていた場合、
出入金停止の措置によって、引き落としができなくなってしまいます。
そうなると、別途、納付書などを使って支払うべきものを支払う手続きをする必要があり、
引き落とし設定していた契約等の数によっては、
その手続きをするだけで、骨が折れること間違いなしです。
ですから、亡くなられた方が生前、葬儀代などは自分の預貯金から出すように、
と言っていたのであれば、相続時口座照会の申し出をする前に、
お金を下ろしておく必要があります(※)し、
口座引き落としになっているもので、把握できているものがあるならば、
契約名義・支払い口座の変更を先にしておくなど、工夫する必要があるでしょう。
放棄手続きの前に、亡くなられた方の遺産に手を付けてしまったということで、
放棄が認められなくなる可能性がありますこと、十分ご留意下さい。
相続手続きとの関係で、この制度の利用が向いている人
預貯金口座付番制度の利用が「向いている」と言えるのは、
どのような方でしょうか。
私見ですが、以下に該当する方だと考えます。
ア:預貯金口座をたくさん持っており、
自分でもどの金融機関に口座を持っているか曖昧になっている方
預貯金口座付番制度を利用することで、
ご自身の名義となっているすべての預貯金口座について、
マイナンバーと紐付けできるようになっているのが、今回の制度強化のミソです。
従って、預貯金口座をたくさん持っていて、かつ、日頃使っていない口座も存在し、
自分でもどの金融機関に口座を持っているのか、曖昧になってしまっている、
という場合には、ご自身が亡くなられた際、ご家族を困らせることのないように、
制度を利用するのが良いと言えるでしょう。
今後も、定期的な入出金(口座引き落としなど)の予定がないようであれば、
お元気なうちに解約して、口座の総数を減らすのも一つの手ではあります。
イ:ネット銀行など、口座の存在がわかりにくい口座を持っている方
最近はネット銀行など、実店舗のない金融機関に口座を持っている方、
また実店舗のある金融機関に口座を持っていても、オンライン通帳を利用することにより、
紙の通帳の発行を受けていない方も増えてきているようです。
紙の預貯金通帳はそれなりの大きさがあり、かつ、実体のあるものですので、
預貯金口座を持っていることに気づきやすいというメリットがあったのですが、
上記に該当する場合、ご家族にとっては口座の存在がわかりにくいと言えます。
残されたご家族が口座の存在を容易に把握することができるようになります。
ウ:ご自身の相続人となるご家族とは別居しており、
ご自身がどの金融機関に口座を有しているか、一切伝えていない方
例えば、「自分は結婚していて、親とは別居しており、
親がどの金融機関に口座を持っているのかわからないし、
話を聞いたこともない」という方が、世の中には結構いらっしゃいます。
日頃から、どの金融機関に口座を持っているのか、話ができていれば別ですが、
そうでない場合、この制度を利用して、
すべての金融機関の口座との紐付けをしておくと良いでしょう。
別居のご家族が相続手続きをするにあたって、まず1箇所、
口座を有していた金融機関を特定して手続きをするだけで、
どの金融機関に口座を有していたのか、口座の総数はいくつなのか、
容易に把握することができるようになります。
相続手続きとの関係で、
この制度の利用が向いていない(または必要ない)人
どのような方が挙げられるでしょうか。
私見ですが、以下に該当する方だと考えます。
ア:金融機関の口座を1つだけしか持っていない方
そもそも論として、ご自身が口座を持つ金融機関が1つだけ、という場合には、
この制度の利用を検討する必要はないと言えます。
紙の預貯金通帳のように、口座の存在が容易にわかるものが存在しない場合には、
別途、メモ書きなどを用意して、もしもの際に口座の存在をご家族に知らせることが、
ご家族のために重要であると言えます。
イ:マイナンバーの制度に懐疑的な方
従って、マイナンバー制度に懐疑的な意見をお持ちの方や、
マイナンバーに関する不安をお持ちの方には、ご利用をお勧めできかねます。
ウ:ご自身の相続人となるご家族に、すべての口座の情報を伝えている方
どの金融機関にご自身名義の口座があるのか、漏れなく伝えられており、
ご家族もきちんと把握できているようであれば、この制度を利用せずとも、
問題なく相続手続きができると考えられます。
エ:遺言書を作っており、その中で、
ご自身が有するすべての金融機関の口座について明記してある方
遺言書を作っていて、例えばその中で、口座ごとに相続すべき人を指定しているなど、
遺言書本文中または財産目録のページで、
ご自身が有するすべての金融機関の口座について明記してある場合、
遺言書をもって口座の特定ができることから、
この制度の利用は検討しなくても大丈夫だと言えます。
口座の情報が一切記載されていない遺言書の場合は、
遺言書によって口座の存在がわからないため、
この制度を遺言書と併用することによって、手続きしやすくすることが考えられます。
オ:被後見人となっている方
成年後見制度などにより被後見人となっている場合、マイナンバーについては、
後見人を引き受けている方が管理している形が考えられます。
この場合、預貯金口座付番制度は「本人の意思」に基づくところ、
後見人が代理人としてこの制度の利用を申し込めるかどうかについては、
現時点では公式な見解が示されていません。
後見人となる方が被後見人となる方の有する預貯金口座について、
すべて確認して管理下に置くため、制度を利用する必要がないとも言えます。
制度を利用する場合の手続きの流れ
どのような流れで手続きを進めるのか、見ていきましょう。
①利用申請(マイナポータルの場合)
マイナポータルで申請する場合は、以下の通りとなります。
| 順序 | 手続き内容 |
| 1 |
マイナポータルにログイン
(ログイン方法について不明な場合は、 マイナポータルの公式サイトにてご確認下さい) |
| 2 |
メニューから「付番の申出」に入る
(公金受取口座の登録とは異なります) |
| 3 |
画面の指示に従って必要事項を入力
|
| 4 |
内容を確認の上、申請
|
| 5 |
預金保険機構から、付番結果について、郵送にて通知が届く
(マイナポータルでの手続きから2~3週間後) |
②利用申請(金融機関の窓口の場合)
金融機関の窓口で申請する場合は、以下の通りとなります。
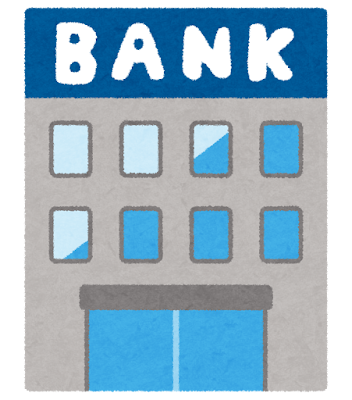
ア:手続きの流れ
| 順序 | 手続き内容 |
| 1 |
金融機関の窓口に行く
(事前の来店予約が必要な場合があります。 各金融機関の公式サイトにてご確認下さい) |
| 2 |
「預貯金口座付番制度を利用する」と伝える
|
| 3 |
係員の指示に従って手続きを行う
|
| 4 |
預金保険機構から、付番結果について、郵送にて通知が届く
(金融機関窓口での手続きから2~3週間後) |
イ:持ち物
マイナンバーカードがあれば、それだけで足ります。
マイナンバーカードを作っていない場合は、マイナンバー通知カードに加え、
以下のいずれかを用意する必要があります。
| 顔写真のある本人確認書類 (右記いずれか1種類) |
・運転免許証
・運転経歴証明書 ・パスポート ・療育手帳 ・在留カード(特別永住者証含む) |
| 顔写真のない本人確認書類 (右記いずれか2種類) |
・健康保険証
・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・印鑑証明書 ・住民票の写し |
③相続時口座照会
相続人が相続時口座照会を申請する場合は、以下の通りとなります。
なお、死亡から10年以内であればいつでも申請可能です。
ア:手続きの流れ
| 順序 | 手続き内容 |
| 1 |
亡くなられた方のマイナンバーを確認する
(マイナンバーの確認が取れないと、申し込みできない場合があります) |
| 2 |
金融機関の窓口に行く
(事前の来店予約が必要な場合があります。 各金融機関のホームページにてご確認下さい) |
| 3 |
係員の指示に従って手続きを行う
(手続きを行う金融機関の口座について、 残高証明書の発行が必要な場合は、同時に手続きができます) |
| 4 |
預金保険機構から、照会結果について、郵送にて通知が届く
(宛先は申込時に指定した相続人の住所) |
| 5 |
通知結果をもとに、適宜、
各金融機関において口座の解約払い戻しなどの手続きを行う (解約払い戻しなどは、各金融機関ごとの手続きが必要です) |
イ:持ち物
持ち物については、一般的に必要と考えられるものを記しています。
金融機関によって異なる場合がありますので、必ず事前に問い合わせて下さい。
- ①亡くなられた方(被相続人)の死亡の記載がある戸籍(または除籍)謄本
- ②手続きをする相続人の現在の戸籍謄本
※配偶者が手続きをする場合は①が②を兼ねます。
※兄弟姉妹が相続人になる場合など、血縁関係を証明するために、
過去の戸籍に遡って取得・提出する必要がある場合があります。 - ③亡くなられた方(被相続人)のマイナンバーカード
- ④手続きをする相続人の印鑑証明書
- ⑤手続きをする金融機関の、亡くなられた方名義の預貯金通帳等
まとめ:預貯金口座付番制度は一考の価値あり
如何でしたか。
ここまで見てきたように、預貯金口座付番制度の利用には向き・不向きがありますが、
将来、ご自身が亡くなられた際の相続手続きに備える観点で、
利用について検討する価値がある制度だと言えます。
当事務所で、相続時口座照会の手続きを代行できます
なお、手前味噌で恐縮ですが、当事務所の「相続手続きサービス」では、
相続時口座照会の手続きを、あなたに代わって行うことができます。
相続時口座照会をはじめとする、一連の相続手続きをお任せいただくことによって、
あなたは相続手続きによる肉体的、精神的な苦労から解放され、
すべての手続きをラクに終わらせることができます。
ぜひご相談下さい。
相続手続きを、あなたに代わって行います。
◆奥田航平行政書士事務所の相続手続きサービスの詳細ご紹介
◆「親」を亡くされた方向け、相続手続きサービスの詳細ご紹介
◆「兄弟姉妹、おじ・おば」を亡くされた方向け、相続手続きサービスの詳細ご紹介
「兄弟姉妹・おじ様・おば様」が亡くなられた場合につきましては、
それぞれ、専用のご案内ページを設けております。
「配偶者」など、上記に当てはまらないご家族が亡くなられた場合には、
一番上の文字リンクをクリックの上、当事務所トップページをご覧下さい。
あなたがすべき具体的な手続きは何か?
無料(※初回相談無料です)で診断いたします。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!

番号をタップすると当事務所にお電話できます↑
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
登録すると…
◆相続・終活に関する情報が得られます
◆当事務所にご依頼の際、特典をご用意いたします

