身寄りのないおひとりさまは臓器提供ができるのか?
画面を横向きにすると見やすくなります。
臓器提供は、身寄りがいなくてもできる?
当事務所では、身寄りのないおひとりさま向けの終活支援をしており、
「おひとりさま向け安心終活プラン」サービスを提供していますが、
ご利用のお客様に、必ずご意向をお伺いしていることがあります。
それは、
- 「脳死判定が出た際などに、臓器提供しますか」
この記事では、上記の通りご意向をお伺いしているのはなぜなのか、をお伝えすべく、
「おひとりさまの臓器提供の可否」について、解説します。
注釈:「身寄りのないおひとりさま」の定義について
一点、この記事における「身寄りのないおひとりさま」の定義ですが、
以下の2つに分けております。
①(狭い意味の)おひとりさま
この記事で「(狭い意味の)おひとりさま」という言葉が出てきた場合には、
・子、孫など直系卑属(養子含む)
・親、祖父母など直系尊属(養親含む)
・兄弟姉妹(養子の兄弟姉妹含む)
・甥、姪
にあたる方がどなたもいらっしゃらない、または全員亡くなられており、
ご自身が亡くなられた際、相続人となる方が一人もいない方を指します。
②(広い意味の)おひとりさま
一方、「(広い意味の)おひとりさま」という言葉が出てきた場合には、
上記①の四角の中に記載しているご親族のどなたかがいらっしゃる方を指します。
例えば、「私は結婚していないし子供もおらず、一人暮らしをしている。
なので、自分は身寄りのないおひとりさまであると考えている。
しかし、疎遠ではあるものの、別居の兄弟姉妹や甥姪はいる」
という方が、この記事における「(広い意味の)おひとりさま」に該当します。
そもそも「臓器提供」とは
なお、本記事の作成にあたっては、臓器の移植に関する法律(通称「臓器移植法」)、及び、
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク公式サイトの記載を参考にしております。
臓器移植とは
臓器移植は、医療行為の一つで、病気や事故などにより臓器の機能が低下してしまった方に、
他者の健康な臓器と、元々の臓器とを交換することで、機能回復を目指すものです。
現在のところ、日本では、
国内で移植手術が行われた件数(年間)…583件(2024年のデータ)
※日本臓器移植ネットワーク公式サイトより数字を引用
ちなみに、最も移植希望者が多いのは腎臓だそうです。
臓器提供とは
臓器提供は、臓器移植法に基づき、上記の通り臓器移植を希望する方に対し、
脳死後、または心停止(死亡)後に、自らの臓器を提供することを指します。
脳死とは
脳死は、病気や事故などにより、脳の機能が全面的に失われ、元に戻らない状態を指します。
「植物状態」と混同されることがありますが、
こちらは脳の機能の一部(特に脳幹部分)が残っており、
自発呼吸ができて、回復の可能性があるという意味で、脳死とは異なります。
脳死した方の場合、いずれは心停止に至りますが、停止までの所要時間はまちまちです。
なお、法的に「死亡」と扱われるのは、臓器提供をしない場合は心停止のとき、
臓器提供をする場合は、医師により2回目の脳死判定が終了したとき、とされています。
日本では、臓器提供の多くが、脳死した方からの提供となっています。
提供できる臓器の種類
臓器ならどれでも提供できるというわけではなく、脳死か心停止(死亡)かにより、
提供できる臓器の種類が以下の通り決められています。
脳死の場合
心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球
心停止(死亡)の場合
腎臓、膵臓、眼球
※腎臓、膵臓は生前からの準備が必須
本人の希望による例外措置
なお、例外として以下の3つが規定されています。
- ①臓器提供は、上記記載の臓器の一部のみを対象とすることができます。
一部のみの提供を希望する場合は、後述の意思表示でその旨を明らかにします。 - ②皮膚、心臓弁、血管、骨など、上記に記載のない体内組織について、
後述の意思表示で特記事項として記載してあれば、提供することができます。 - ③一定の条件を満たせば、
ご自身の親族に優先的に提供する取り扱いとすることができます。
この場合、その旨を後述の意思表示で明らかにします。
※特定の一人のみを指名する意思表示(提供先の限定)はできません。
※医学的な条件により、希望が叶わない場合もあります。
※自殺者については、臓器の親族への優先提供は行われません。
臓器提供の意思表示について
自らの臓器を提供したいかどうかについては、意思表示をすることが可能です。
この意思表示は任意となっています。
「臓器提供したくない」という意思表示も、もちろん可能です。
意思表示と年齢
意思表示については年齢による制限があります。
具体的には、「提供したくない」という意思表示に年齢制限はありませんが、
「提供したい」という意思表示は、満15歳以上でなければ法的に無効となります。
意思表示の方法
意思表示をする場合、

- 意思表示カード(日本臓器移植ネットワークに
問い合わせればもらえるほか、
市区町村役場、病院などで
配布されている場合があります) - 運転免許証(裏面に記載欄あり)
- マイナンバーカード(表面に記載欄あり)
のいずれかに記載することができます。
原則、本人が手書きする必要がありますが、手が不自由であるなど特別な事情がある場合、
立会人を手配することで、代理人による代筆ができます。
インターネットで意思登録するページがあり、
そちらを利用して、オンラインで意思表示することもできます。
家族の承諾による臓器提供について
上記の通り、本人による意思表示が任意である点や、年齢制限が設けられていることから、
本人が臓器提供を望んでいるのかどうか、不明な場合があります。
そのような状況下で脳死の判断がなされた場合は、家族が承諾すれば、
臓器提供が可能という取り扱いになっています。
ここでいう「家族」は、原則として、
を指し、承諾する場合は、その総意を書面で示すことが必要です。
「総意」が必要なため、上記の方のうちどなたか一人でも反対する方がいれば、
承諾とはならず、臓器提供は行われないこととなります。
兄弟姉妹や甥姪がいるという場合、それらの方が「家族」に含まれることとなります。
脳死の場合における臓器提供の流れ
脳死の場合には、一般的に以下の流れに沿って臓器提供が行われます。
| 順序 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 入院・治療 | まずは入院の上、必要な治療が行われます。 |
| 2 | 主治医の説明 |
主治医が、脳死の可能性があり、 回復の見込みがないことを説明します。 |
| 3 |
コーディネーターの 説明 |
主治医の説明を受け、家族が希望した場合、 日本臓器移植ネットワークのコーディネーターが、 病院を訪れ、家族に対し、 臓器提供の制度を説明します。 (本人が事前に意思表示をしていたかどうかは、 この段階で確認 〔運転免許証への記載などをチェックします〕) |
| 4 | 家族の判断 |
家族で話し合いを行い、 臓器提供の可否を総意として決めます。 |
| 5 | 脳死判定 |
家族が臓器提供を承諾した場合、 主治医等が、臓器移植法に基づき、 脳死判定を2回行います。 2回目の判定終了時をもって、死亡となります。 |
| 6 | 移植患者の決定 |
日本臓器移植ネットワークにより、 移植する臓器の種類、移植する患者を決定します。 |
| 7 | 臓器摘出 | 移植対象となる臓器を摘出します。 |
| 8 | 遺体の引き渡し |
家族に遺体が引き渡されます。 併せて、主治医から死亡診断書が発行されますので、 これをもって、死亡届の提出や葬儀など、 相続を含めた死後の手続きが可能となります。 |
身寄りのないおひとりさまの臓器提供の可否
では、ここから本題です。
身寄りのないおひとりさまは、自らの臓器を提供することができるのでしょうか。
その答えは、以下の表の通り6つに分けて考えることができます。
| (狭い意味の) おひとりさま |
(広い意味の) おひとりさま |
|
|---|---|---|
| 本人の 「提供する」 意思表示あり |
○ |
○ ※ただし、家族のうちお一人でも 反対の人がいれば × |
| 本人の 「提供しない」 意思表示あり |
× | × |
| 本人の 意思表示なし |
× |
○ ※家族全員の同意が条件 |
具体的に見ていきましょう。
①「『提供する』意思表示をしている」(狭い意味の)おひとりさま
日本臓器移植ネットワークによると、ご家族がどなたもいらっしゃらない場合、
「ご本人の意思表示があれば、その意思が尊重されます」とのことです。
それを病院関係者に示しておけば、臓器提供の意思を実現できることになります。
②「『提供しない』意思表示をしている」(狭い意味の)おひとりさま
その意思が尊重されます」という扱いになることから、
臓器提供を望まない意思表示をしている以上、臓器提供は行われないこととなります。
③「意思表示をしていない」(狭い意味の)おひとりさま
お元気なうちに意思表示をしていなかった場合は、
臓器提供を望むのかどうかがわかりませんし、
承諾を求める家族もいないということで、臓器提供は行われないこととなります。
④「『提供する』意思表示をしている」(広い意味の)おひとりさま
(広い意味の)おひとりさまの場合には、上記3つと異なり、
承諾するかどうか判断する家族がいらっしゃいます。
そのため、基本的にはお元気なうちの意思表示が尊重されるのですが、
家族の承諾が、実際に臓器提供をするためには不可欠なプロセスとなっています。
先ほども説明した通り、家族の承諾は「家族の総意」であることが必要です。
そのため、家族の中にお一人でも、臓器提供に反対の方がいる場合、
本人の意思に反して、臓器提供が実現しない、という点には注意が必要です。
事前に話をして理解を求めておくのが良いでしょう。
⑤「『提供しない』意思表示をしている」(広い意味の)おひとりさま
しかし、家族が臓器提供を承諾する意向であっても、
本人が事前に「臓器提供したくない」という意思表示をしていた場合には、
本人の意思が優先され、臓器提供は行われないこととなります。
日頃家族と疎遠である、あるいは仲が悪いとしても、
下記⑥のように「意思表示をしていない」と誤解されることのないように、
「提供しない」意思表示をしていることを伝えておくことが望ましいです。
⑥「意思表示をしていない」(広い意味の)おひとりさま
一方、(広い意味の)おひとりさまに該当する場合で、
お元気なうちに意思表示をしていなかった場合は、先ほど説明した通り、
家族の承諾によって臓器提供が可能になるという扱いになります。
ご家族にとって酷なことが多いと言われています。
そのため、お元気なうちに意思表示をしておくことが望ましいと言えます。
臓器提供と(生前の)委任契約との関係
おひとりさまを支える各種の契約などとの関係について、ご紹介します。
まずは、「(生前の)委任契約」との関係についてです。
(生前の)委任契約とは
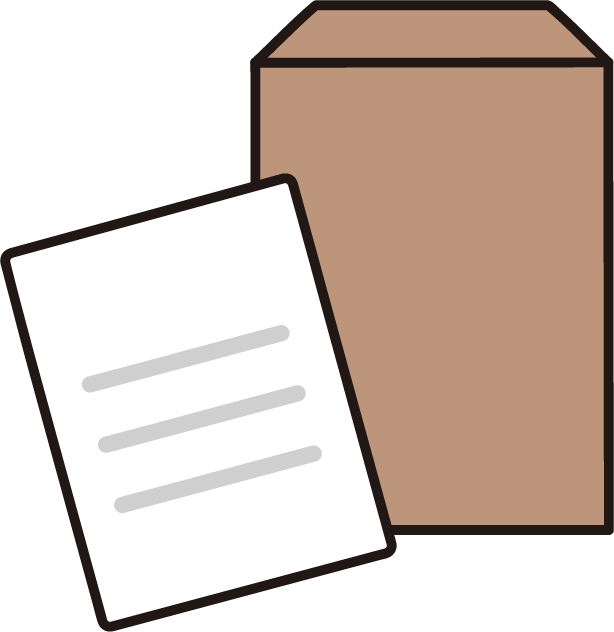
(生前の)委任契約は、身寄りのないおひとりさまがご生存中、
安心して過ごすことができるように、
- 定期的な連絡や面談、災害発生時等における安否確認など
- 入院する際の手続きサポート
- 長期間、自宅を留守にする際の財産管理や自宅の見回り など
を、信頼できる第三者にお願いすることを目的とした契約です。
(まれに、臓器提供の承諾をし得る家族を受任者として契約する場合がありますが、
この記事では、血縁関係のない人と契約する想定で解説します)
ちなみに当事務所では「見守り・財産管理等委任契約」と呼んでいます。
(狭い意味の)おひとりさまの場合
パターン1 事前の「提供する」意思表示あり
この場合は、先ほどご紹介した通り、「ご家族がどなたもいらっしゃらない場合は、
ご本人の意思表示があれば、その意思が尊重されます」という、
日本臓器移植ネットワークの見解に沿って対応が行われることになりますので、
臓器提供の意思が実現することとなります。
(生前の)委任契約の受任者は、あくまで「第三者」であることから、
承諾を要する家族には該当しないため、
受任者が臓器提供の可否を判断することはありません。
ただし、受任者が主治医などに対し、本人(委任者)の運転免許証などを見せて、
「以前、臓器提供の意思表示をしていました」と説明する必要があるかも知れませんので、
事前に、受任者に対し、意思表示をしていることを伝えておく必要はあります。
このことが、冒頭でお伝えした、
当事務所の「おひとりさま向け安心終活プラン」をご利用のお客様に、
臓器提供のご意向を必ず確認している大きな理由なのです。
なお、(生前の)委任契約は、臓器提供が行われる場合、
2回目の脳死判定終了時をもって死亡と扱われることから、
この時をもって終了することとなります。
これは、(広い意味の)おひとりさまから臓器提供が行われる場合も同様です。
パターン2 事前の「提供しない」意思表示あり
一方、この場合は、本人(委任者)が「提供しない」と言っている以上、
臓器提供は行われないこととなります。
(生前の)委任契約の受任者は、本人(委任者)が心停止により死亡するまで、
受任者として、契約内容に基づく業務を行うことになります。
パターン3 事前の意思表示なし
この場合は、先ほどご紹介した通り、本人(委任者)の意思が不明である上に、
承諾権限のある家族もいないことから、臓器提供は行われません。
(生前の)委任契約の受任者は、本人(委任者)が心停止により死亡するまで、
受任者として、契約内容に基づく業務を行うこととなり、
臓器提供の承諾を求められることはありません。
口頭でその意思を伝えておくだけでは、意思表示とはみなされませんので、
運転免許証の裏面にある記載欄に記入するなどしておく必要があります。
(広い意味の)おひとりさまの場合
パターン4 事前の「提供する」意思表示あり
(広い意味の)おひとりさまの場合は、承諾権限のある家族が存在することから、
本人(委任者)の事前の意思表示を踏まえつつ、最終的には、
家族の承諾の有無によって臓器提供の可否が決まる形となります。
受任者は、契約に基づいて本人(委任者)の運転免許証などを預かっている場合、
ご家族に対して「臓器提供の意思表示をしている」ことを伝えることはできますが、
承諾するか否かを決定する場に参加することはできません。
パターン5 事前の「提供しない」意思表示あり
この場合は、先ほどご紹介した通り、臓器提供が行われることはありません。
(生前の)委任契約の受任者は、本人(委任者)が心停止により死亡するまで、
受任者として、契約内容に基づく業務を行うことになります。
パターン6 事前の意思表示なし
家族が、承諾するかどうかを決める場に、受任者が参加できないのは、
上記パターン4と同じです。
臓器提供と任意後見契約との関係
任意後見契約とは
任意後見契約は、認知症などで判断能力を失ってしまった際に、
- 財産管理
- 身上監護(介護施設への入所手続きなどを本人に代わって行うこと)
をお願いする第三者を、元気なうちに決めておき、
その方にこれらの事務を引き受けてもらうことを約束することを目的とした契約です。
認知症を発症するなどした場合に、任意後見契約に基づく法的サポートに、
移行していくという形が取られています。
臓器提供との関係
任意後見契約と臓器提供との関係ですが、基本的には、
上記(生前の)委任契約の項目で触れた、パターン1から6と同様になります。
重要なポイントとしては、
- 任意後見契約の受任者、任意後見人及び任意後見監督人に、
臓器提供について承諾する権限はない - 任意後見契約に基づく任意後見人の業務は、
2回目の脳死判定終了時または心停止時(死亡)まで続く
※被後見人死亡による後見業務終了の手続きは別途必要 - 任意後見契約の受任者、任意後見人は本人(委任者)の死亡届を提出できる
意思表示の時期に注意
一点気をつけたいのが、本人(委任者/被後見人)が意思表示をした時期です。
認知症などで判断能力を失った状況下で、臓器提供についての意思表示をしても、
本人(委任者/被後見人)が趣旨を理解した上で意思表示しているのかどうか、
疑問を呈され、結果、臓器提供につながらなくなるのは、当然の帰結と言えます。
そのため、本人(委任者/被後見人)が元気なうちに意思表示をしておくことはもちろん、
運転免許証などに記入する際、記入日を忘れずに書いておくことが重要です。
後見が開始した日よりも前であれば、その意思表示は有効なものとみなされ、
本人(委任者/被後見人)の希望が叶うこととなります。
臓器提供と尊厳死宣言公正証書との関係
尊厳死宣言公正証書とは
尊厳死宣言公正証書は、自らが病気により回復の見込みがなくなった場合に、
延命治療を控え、または行わず、自らの尊厳を保ったまま、自然な死を迎えたい、
という意思を、主治医などに伝えるためのものです。
作成を希望する人が、公証役場に依頼することで作ることができます。
主治医などは、尊厳死宣言公正証書の内容について、基本的には尊重してくれますが、
あくまで医学的な判断によって治療は行われますので、
望んでいる通りの最期を迎えられるとは限らない点、事前の理解が必要です。
尊厳死宣言公正証書に臓器提供の意思表示はできる?
尊厳死宣言公正証書と臓器提供の意思表示は、全く別個のものであることから、
尊厳死宣言公正証書の中で、臓器提供の意思表示をすることはできません。
ただし、「臓器提供したくない」という意思表示をしている場合には、
「臓器提供はしない。私が脳死の状態になったとしても、延命治療は行わず、
しかし緩和ケアは行って、自然な死を迎えられるようにして下さい」
という一文を入れることは、可能であると考えます。
上記のような趣旨の尊厳死宣言公正証書を作りたいとのご相談を受け、
公証人の先生にその旨お伝えし、作ってもらったことがあります。
臓器提供と献体との関係
最後に、献体との関係を確認していきましょう。
日本臓器移植ネットワークでは、臓器提供と検体の双方を希望することは可能である、
という見解を示しています。
ただし、献体の受け入れを行う大学等では、大半の大学等が、
献体登録希望者が臓器を提供する旨の意思表示をしている場合、
献体登録自体を断っています(臓器提供後の遺体は解剖実習に不向きなため)。
そのため、事前に大学等に確認する必要があります。
身寄りのないおひとりさまは献体ができるのか?
まとめ:身寄りのないおひとりさまが臓器提供を希望するなら、
事前の調整をきちんとしよう
如何だったでしょうか。
臓器提供は、臓器移植を待ち望む方の役に立つ、社会的に意義のある行為だと思います。
だからこそ、おひとりさまであるか否かを問わず、臓器を提供したい気持ちがあるなら、
積極的にその意思を表明してほしいと願っています。
ただし、ここまで見てきた通り、意思が確実に確認できることが重要ですので、
- (狭い意味の)おひとりさま
→(生前の)委任契約、任意後見契約の受任者となってくれる方に、
臓器提供に関する意思表示をしていることを必ず伝えておきましょう - (広い意味の)おひとりさま
→第三者との間で(生前の)委任契約、任意後見契約を締結するとしても、
臓器提供については家族の承諾が不可欠になるので、
たとえ家族と疎遠、あるいは仲が悪いとしても、
臓器提供に関する意思表示をしていることを必ず伝え、理解を得ておきましょう
(まだ意思表示していないなら、今から意思表示しましょう)
当事務所では、する・しない、どちらのご意思も尊重してサポートします
なお、手前味噌で恐縮ですが、当事務所では、
「おひとりさま向け安心終活プラン」の中で、臓器提供を希望する、しないに関わらず、
身寄りのないおひとりさまのサポートを行っております。
また、サポート内容を、臓器提供ご希望の有無に合わせて調整することができます。
生前の見守りから死後の葬儀、遺品整理など、
不安なことを専門家とともに解決しませんか?
ぜひ、無料(※初回相談無料です)のご相談をお受け下さい。
ご相談は土日祝日可!ご自宅への出張OK!ご予約受付中です!

番号をタップすると当事務所にお電話できます↑
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
登録すると…
◆相続・終活に関する情報が得られます
◆当事務所にご依頼の際、特典をご用意いたします

