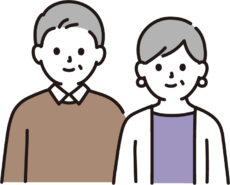現在、多数のご依頼をいただいており、業務処理能力の限界に達しております。
そのため、大変心苦しいのですが、新規のご相談ご予約について、
一時的に受付をストップしております。
期間は、このお知らせが消えるまで(目安は未定です)となっております。
誠に恐れ入りますが、何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
こんなお悩みはありませんか?
- ①最近もの忘れが増えてきました。
近い将来認知症になってしまう可能性が正直あるのですが、
認知症になった時に、自分の財産をきちんと管理できるのか不安です… - ②私には子供が1人いますが、海外に住んでいます。
なので、入院や、介護施設への入居が必要になっても、
その子がすぐには帰国できないので、
自分自身でこれらの手続きができない場合、どうしたら良いのでしょうか… - ③もし自分が認知症になったら、成年後見制度の法定後見を利用して、
後見人さんに財産管理などをお任せできるそうですが、
後見人さんは基本、裁判所で選ばれるので、見ず知らずの人が選ばれる可能性があると言うし、
横領やら家族との対立やら、良くない話をたくさん聞きます。
なので、見ず知らずの人に私の後見人さんにはなってほしくないです…

もし、このようなお悩みをお持ちでしたら、
終活・相続対策専門事務所である当事務所が、きっとお役に立てます。
さて、厚生労働省の調査によると、認知症の患者数は年々増えており、今後も増加傾向だと言います。
2022年→約443万人(65歳以上の高齢者の約12%)
2030年→約523万人(65歳以上の高齢者の約14%)
2050年→約587万人(65歳以上の高齢者の約15%)
(出典:内閣官房「認知症施策推進関係者会議(第2回)」配付資料)
認知症は、誰がなってもおかしくないと言われています。
ですから、想像してみて下さい。
もし、あなたご自身が認知症になってしまったら、どのような問題が起きるでしょうか。
認知症になってしまった場合の、代表的な3つの問題点
1.自分の財産を適切に管理できなくなり、銀行側で口座が凍結されることも
一口に「認知症」と言っても、言語障害や運動機能障害など様々な症状がありますが、
法的な観点から最も問題となる症状は、「判断力の低下」です。
(判断力の低下は記憶障害や遂行機能障害などと相まって、どんどん低下していきます)
判断力が低下してしまうと、自分が何をしているのか、何をしようとしているのかが正確にわからなくなってしまうため、
特に、ご自身の財産を適切に管理できなくなってしまうというリスクが高まります。
例えば、
- ①あるモノを買ったことを忘れてしまい、同じモノを繰り返し購入してしまう
(→必要以上にお金を使ってしまう) - ②預金口座の暗証番号やATMの操作方法がわからなくなり、
自分の口座から必要なお金を引き出せなくなる - ③現金や預金通帳をどこに置いているかわからなくなり、
結果、外出や買い物が困難となることで、他人の助けなく生活することが困難になる
といったことが起こり得ます。
銀行側の判断で口座を凍結してしまう事例もあるといいます。
こうなると、もはや、自力ではどうにもできなくなってしまいます。
2.自力で契約や手続きをすることが難しくなり、悪質商法や詐欺の被害に遭うリスクも
また、判断力の低下によって、下記のような行為も、自力ではしにくくなってしまいます。
- 市区町村役場などでの行政手続き
- 入院する際の手続き
- 介護施設を利用(老人ホーム等へ入居、デイサービスの新規利用など)する際の契約
- 売買、贈与、賃貸借などの契約
- その他、法的効果の生じる行為(遺産分割協議など)
この点、同居のご家族がおり、ご家族の助けを受けながら、あるいは家族に代わりにしてもらえれば、
自力でできなくても、特に困ることはないでしょう。
しかし、家族が全員遠方に別居しているなど、様々な事情で、頼ることが難しい場合もあります。
そうなると、極力自力で手続きや契約をしなければならなくなりますが、
認知症になってしまうと、それが困難になってしまうのですから、このままだと八方塞がりです。
悪質商法や詐欺の被害に遭うリスクも高まります!
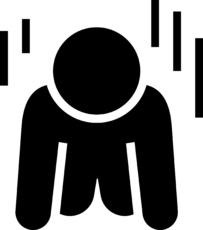
さらに、判断力が低下するということは、それが正しいことなのか、
自分に何らかの損害をもたらすものではないか、を判断することも困難になる、
ということです。
そのため、悪質商法や詐欺の被害に遭うリスクも高くなります。
当事務所代表も、これまでに、
- 明らかに不要なモノを高額で売りつけられる
- 売るつもりのないモノを強引に、かつ安価で買い取られる
- 怪しい投資話に乗せられ、数百万円をだまし取られる
このような被害から身を守ることも、何もしていなければ難しくなってしまうのです。
3.法定後見制度もあるけれど、評判が…
なお、「こんなお悩みはありませんか?」の③で触れた通り、認知症等で判断力が低下した方のための制度として、
「成年後見制度」というものがあります。
ここでいう「成年後見制度」は、具体的には「法定後見」と呼ばれるものを指し、
- ①認知症、その他の障害により、判断能力が不十分な方について、医師の診断のもと、
本人(被後見人といいます)に代わって後見人が財産管理や身上監護を行うことを目的とする制度 - ②認知症等の診断を受けた後、家庭裁判所に申立てを行うことにより、裁判官が後見人を選任する
- ③そして、後見人が財産管理等をすることで、被後見人を法的に保護・支援する
といった特徴があります。
なお、家庭裁判所に法定後見の申立てをする際、誰を後見人とするかについて、
特定の人(例えば被後見人となる方のご家族)を候補者として推薦することは、可能になっています。
しかし、審理の過程で、その候補者が後見人としてふさわしいかどうか、厳しく審査され、
家庭裁判所において「適当ではない」と判断されてしまうと、見ず知らずの人(主に弁護士)が選ばれる結果となります。
しかも、家庭裁判所の決定は絶対ですので、仮に見ず知らずの人が後見人に選ばれたとしても、
それを理由として、後見人の交代を求めたり、法定後見の申立てそのものを取り下げることはできない仕組みです。
そのような制度設計のため、法定後見は評判が悪いのです。
さらに、こんなトラブルに巻き込まれることも…
家庭裁判所が後見人を選ぶ場合、ほとんどのケースでは弁護士等の専門家が選ばれます。
選ばれた専門家は、真面目に仕事をする方が多いものの、中には…
- 本人(被後見人)や家族とのコミュニケーションが不足し、もめ事を起こしてしまう
- 本人(被後見人)の財産を守ろうとするあまり、家族の日常生活に過剰に介入してしまう
- 本人(被後見人)の財産を横領し、逮捕されてしまう
といったトラブルに発展してしまう場合が、一定数生じているのが実情です。
これもまた、法定後見の評判を落としてしまっている一因なのです。
認知症に対して法的に備えたいなら、当事務所にご相談を

申し遅れました。
私は、東京都葛飾区で「相続・遺言パートナー」として活動している、
相続専門行政書士の奥田 航平と申します。
私が代表を務める「奥田航平行政書士事務所」は、2014年8月の開業以来、
相続専門の事務所として、
終活や将来の相続対策を頑張りたいお客様のサポートをして参りました。
現在は、「お客様の終活をサポートする」活動の一環として、
認知症に対する法的対策をしたい方のサポートに、一層力を入れております。
「認知症に対する法的対策をする上で、大事な3つのポイント」をお伝えします。
認知症に対する法的対策をする上で、大事な3つのポイント
1.「信頼できる人」を見つけ、その人との間で「財産管理をしてもらう契約」をしましょう
まず大事なことは、
- ①認知症になった時に財産管理を任せられる、信頼できる人を見つける
- ②その人に、自分が認知症になってしまった時に財産管理をお願いすることについて、了承を得る
- ③そして、了承を得たことを証するため、契約をする
ことです。
順番に見ていきましょう。
①認知症になった時に財産管理を任せられる、信頼できる人を見つける
先ほどご紹介した「法定後見」では、裁判所で選ばれた見ず知らずの人が後見人になる可能性が高いです。
そのため、いきなり見ず知らずの人に財産の管理を委ねることになり、不安になって当然ですし、
いくら「後見の専門家」と言えども、なかなか信頼しにくい場合もあろうかと思います。
だからこそ、ご自身で、お元気なうちに、
認知症になった時に財産管理を任せられる、信頼できる人を見つけることがとても大切です。
そうすれば、認知症になっても財産管理の面で安心できます。
②その人に、自分が認知症になってしまった時に財産管理をお願いすることについて、了承を得る
ただ、見つけた「信頼できる人」が、必ず後見人を引き受けてくれるとは限りません。
ですので、
・後見人がどのような役割を果たすのか
・引き受けてくれる場合に、どのようなお礼を用意するか
などを丁寧に話し、相手方の理解を得て、了承してもらうことが必要です。
(固辞された場合には、別の「信頼できる人」を探すことも必要でしょう)
この「丁寧に話す」ことを大切にすることで、「信頼できる人」があなたと近しい関係であればあるほど、
あなたの想いを理解し、引き受けてくれる可能性が高まるでしょう。
③そして、了承を得たことを証するため、契約をする

そして、了承を得られたならば、
口約束で終わらせず、契約をすることが重要です。
この契約のことを「任意後見契約」といいます。
ではなぜ、契約をする必要があるのでしょうか。
その理由は、後見人が財産管理をする場合、
銀行での取引などを行うことになりますが、銀行などの立場からすれば、契約書など、
あなたがその方に財産管理を任せたという証拠がなければ、取引の申し出を受けるわけにはいかないからです(犯罪防止のため)。
結果としてあなたの財産を守ることにつながる、ということなのです。
2.介護施設の入居手続きなどを親族に頼めるかまず確認し、無理そうなら任意後見契約を活用しましょう
一方、入院や介護施設への入居など、各種の手続きや契約については、手続き・契約先によっては、
一定の範囲の親族(同居のご家族でなくてもOK)が代わりに手続きできる、としている場合があります。
(例えば、特別養護老人ホームに入居する場合、入居する方の子供が手続きをすることは基本的にOK)
このように、手続き・契約先が一定の範囲の親族による手続き・契約を認めているならば、
先ほど申し上げました「任意後見契約」は必要なく、当然に親族の方に手続き・契約を任せられますので、
まずは、親族の方に、手続き・契約を任せられるかどうか、確認してみましょう。
(確認をする相手があなたの配偶者など、あなたのことをよく知っていて、信頼できる親族であれば、
口頭での確認→口約束でも、特に問題はないでしょう)
しかし、「こんなお悩みはありませんか?」の②で触れたように、子供が海外にいてすぐに戻れないなど、
何らかの事情があって、手続き・契約を親族の方に任せられない場合もあろうかと思います。
また、親族の方がいるものの、全員が別居、かつ一番近しい方でも「甥・姪」となるなど、
関係性が薄い場合には、口頭での確認→口約束では不十分と言えます。
そんな時に役立つのが、先ほどご紹介した「任意後見契約」です。
任意後見契約は、財産管理のほか、手続き・契約を任せることも可能です。
そこで、手続き・契約を任せることを目的とした任意後見契約を結んでおけば、
あなたが認知症になってしまっても、手続き・契約を任せることができるのです。
認知症になってしまっても安心することができます。
3.任意後見契約なら見知らぬ人に財産管理される心配がないので、この制度を大いに活用しましょう

なお、任意後見契約を結ぶと、東京法務局にて「後見登記」がなされます。
そして、この「後見登記」がなされている場合、よほどの特殊事情がない限り、
家庭裁判所において法定後見の審判を受けることができません。
つまり、任意後見契約は、法定後見に優先する仕組みとなっています。
先ほど申し上げました通り、任意後見契約は、
あなたが「自分が認知症になってしまった時に、財産管理や手続き・契約を任せたい、
信頼できる人」との間で、任せる内容を明記した上で結ぶ契約です。
ですから、法定後見と異なり、見ず知らずの人が後見人になることがありません。
これが、任意後見契約と法定後見を比較した時の大きなメリットの一つなのです。
なお、任意後見契約によって後見人となることをお願いした方が、きちんと後見人の務めを果たせるように、
あなたが認知症となり、実際に後見を行うこととなった時は、家庭裁判所により「任意後見監督人」が選ばれます。
監督人の方が、後見人の方をサポートすることで、あなたの後見が問題なく進められるようにする仕組みです。
この制度を大いに活用することで、
認知症対策、ひいてはあなたの終活を前に進めることができます。
当事務所の任意後見契約サービス 3つの特徴
1.任意後見契約を結ぶため、制度説明から契約まで全面サポート
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が、任意後見契約を全面的にサポートします。
サービス面で特に注目いただきたいのが、以下の3つです。

(1)後見人となる方にも、制度趣旨や負担の内容などをしっかりご案内
任意後見契約をする際に大事なことは、
- ①あなたご自身が任意後見契約の趣旨を理解すること
- ②後見人をお願いする、信頼できる人を見つけること
- ③見つけた「信頼できる人」に、後見について理解してもらえること
の3つです。
この中で特に大事なのが③です。
先ほど「大事な3つのポイント」の1つ目でご案内した通り、あなたから、ご自身の想いを丁寧にお話いただくのはもちろんのこと、
お相手にもまた、任意後見の制度趣旨や、後見人として財産管理などをする場合にどのようなことをすれば良いのか、
どの程度の負担が発生するのか、などを、しっかりと理解していただくことが大切です。
そこで当事務所では、あなたが選ばれた「後見人をお願いしたい方」に対しても、
制度趣旨などを、誰よりもわかりやすく説明する機会を設け、疑問や不安を解消してもらうことで、
お相手の方が後見人となることを引き受け、契約が締結できるよう、丁寧に進めていきます。
これにより、お互いにしっかりと制度趣旨を理解した上で任意後見契約を結べます。
(2)あなたの手間を最小限にします
法律の規定により、任意後見契約を結ぶ場合には、「公証役場」で契約しなければならない、とされています。
しかし、公証役場にいきなり行っても、その場では契約書を作ってもらえません。
そこで当事務所では、
- 契約書の文案作成
- 公証役場に提出する書類の取得(住民票の写しなど)
※印鑑証明書については、あなたやお相手の方から印鑑登録証をお預かりした場合のみ、
当事務所で取得いたします。ご自身にて取得いただくことも可能です。 - 公証人の先生との事前打ち合わせ、契約締結の日時予約
といった、任意後見契約をするために必要な手続きをすべて行います。
これにより、あなたのご負担は、
- ご相談の場において、任意後見契約について理解いただくとともに、ご希望をお伝えいただく
- 当事務所にて作成した文案をチェックいただく
- 契約締結日に、公証役場に足をお運びいただく
のみとなりますので、最小限の手間で任意後見契約をすることができます。
(3)契約締結時も同伴しますので、最後まで安心です
通常、任意後見契約を締結する際は、公証人の先生とあなた、後見人を引き受けてくれるお相手の方、
以上3人のみで契約書の読み合わせ、署名や押印といった作業を行います。
その点、当事務所では、当事務所代表が必ず公証役場に同伴いたします。
また、公証人の先生の許可が得られれば、同席し、契約締結を見守ります。
無事に契約が締結されるまで、当事務所代表がそばにおりますので、
何の心配をすることもなく、任意後見契約を結べます。
公証人の先生に、あなたのご自宅等に出張してもらって、任意後見契約を締結する形を取ることもできます。
その場合の手配も当事務所で行いますので、ご安心下さい。
2.あなたのご希望も踏まえ、「どんなことを任せるか」具体的にご提案
続いて、こちらの表をご覧下さい。
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| 後見人の職務 | 法律により決まっています |
任意後見契約の中で、 自由に指定することができます |
このように、任意後見契約では、法定後見と異なり、
後見人を引き受けてくれる方に、あなたが認知症になった際、どのようなことをお任せするのか、
ご自身のご希望に基づいて、自由に指定することができる仕組みとなっています。
つまり、オーダーメイドができる、ということです。
このことから、例えば、「長男Aは海外に住んでいて、そう感嘆には帰国できないので、自分がもし認知症になったら、
友人のBさんに、老人ホームへの入居手続きを任せたい」とご希望の場合、
そのことを契約書の中に明記することで、Bさんに、入居手続きをしてもらうことが可能になります。
(逆に言うと、明記されていないと、手続きを任せることができません)
当事務所では、このような任意後見契約の特性を踏まえ、あなたのご希望をしっかりとお伺いし、
かつ、あなたを取り巻く状況や財産の内容、手続き・契約の必要性を踏まえ、
「どんなことを任せるのか」を、具体的ににご提案いたします。
3.信頼できる人が身近にいなければ、当事務所代表をご指定いただけます
なお、後見人をお願いできる、信頼できる人が身近にいらっしゃらないようでしたら、
当事務所代表(行政書士 奥田航平)が、そのお役目を承ることができます。
当事務所代表があなたの後見人となる場合には、法律専門職としての知見を生かし、
あなたの財産を適切に管理し、必要な手続き・契約を迅速に進めることをお約束いたします。
これにより、ご親族やご友人などに、頼れる方がいらっしゃらなくても安心です。
なお、当事務所代表が後見人(受任者)としてあなたとの間に任意後見契約を締結する場合、
以下の3点について、ご理解・ご了承をお願いしております。
- ①当事務所代表による後見人のお引き受けは、
「おひとりさま向け安心終活プラン」をご利用のお客様を優先しております。
そのため、ご希望に副いかねる場合がございます。
現時点においてお引き受け可能かどうかは、お問い合わせの際にお伝えいたします。 - ②契約締結後、あなたが認知症になられ、当事務所代表が後見人として職務を行うに至った場合は、
別途、後見人職務を行ったことに対する料金を、毎月お支払いいただきます。
また、任意後見契約の締結後、あなたに認知症の症状が出ていないか、認知症以外の病気などにより、
判断能力を欠く状況になっていないかを確認するため、別途、「見守り」を行うことを目的とした、
「委任契約」を締結いただきます。
この「委任契約」では、定期的な面談などを行いますが、その都度、所定の料金が発生いたします。
さらに、必要に応じて、民間警備会社等のセキュリティサービスをご利用いただきます。
金銭的なご負担が発生いたしますこと、あらかじめご承知おき下さい。 - ③当事務所代表の身に不測の事態が生じ、後見人としての業務ができなくなってしまう可能性に考慮し、
当事務所では必ず、予備受任者をご紹介し、その方ともご契約いただいております。
予備受任者には、当事務所代表と同じく行政書士をしている者をご紹介いたします。
その他、当事務所にご依頼いただく3つのメリット
1.「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」がモットーです

当事務所は「わかりやすく、丁寧に、スピーディーに」をモットーに、
任意後見契約サービスを提供しております。
具体的には、
①わかりやすく
当事務所では、
- 口頭でのご説明は、わかりやすく言い換えるなど工夫する
- ご記入をお願いする書類には記入例をご用意するなどして書きやすくする
- お渡しする文書では、文字の大きさや表現、色合いなどを十分に調整する
といった、あなたにわかりやすく情報をお届けするための努力をしております。
特に、口頭説明のわかりやすさは、これまでご利用いただいたお客様のみならず、同業者からもお褒めの言葉をいただきました。
ですので、任意後見契約に疑問のある方やご高齢の方も、
任意後見契約の仕組みについてしっかりと理解した上でお任せいただけます。
②丁寧に
先ほど申し上げました通り、任意後見契約の内容はオーダーメイドで作ります。
だからこそ、あなたのお気持ちを丁寧に聞き、あなたの状況を踏まえ、最適な内容をご提案いたします。
この「丁寧に」の姿勢を貫くことで、安心して当事務所代表にお任せいただけます。
③スピーディーに
なお、任意後見契約サービスでは、あなたに判断能力が備わっていることが求められますので、
あなたご自身がお元気であることが絶対条件となります。
だからこそ、一日でも早く契約を結ぶことがとても大切なのです。
一日でも早く契約ができるよう、効率よく進めます。
ですので、お元気なうちに任意後見契約を結ぶことができます。
2.遺言書作成サービスなど他のサービスとの併用も可能です
任意後見契約サービスは、遺言書作成サービス(公正証書遺言の作成)など、任意後見契約と同じく、
公証役場での手続きが伴う当事務所の終活関連サービスと併用いただくこともできます。
ですので、例えば、遺言書と任意後見契約を同時期に作りたい場合、両サービスを同時にお申し込みいただければ、
あなたに公証役場においでいただく(または、公証人の先生にあなたのご自宅等に出張してもらう)のを、
両方併せて一度にまとめることができます。
これにより、あなたのご負担を減らして、終活を効率よく進めることができます。
3.フットワークの軽さが自慢!土日祝日含め出張相談承ります
ご相談の日時については、可能な限りあなたのご希望に合わせております。
土日祝日でも、もちろんご対応可能です。
時間帯も、あなたのご希望にできるだけ沿えるようにしております。
また、ご相談の場所については、
- 来所(あなたに当事務所までお越しいただく)
- 出張(あなたのご自宅など、ご指定の場所に当事務所代表がお伺いする)
のどちらかからお選びいただけます。
あなたのご希望に合わせて場所が選べますので、より相談しやすくなっております。
ちなみに、オススメは、断然「出張相談」です
あなたのご自宅など、ご指定の場所に当事務所代表がお伺いする「出張相談」は、
- ①あなたにとって居心地の良い場所で相談できるので、話しやすい
- ②当事務所まで足を運ぶ手間、時間、費用がかからない
- ③ご相談にあたりご用意をお願いするものを持ち運ばなくて済むので、なくしてしまうリスクがない
など、来所相談と比べて、あなたにとってのメリットが多くございます。
当事務所代表(奥田航平)は、どこへでも喜んで参ります。
「来てもらうのは申し訳ない」などと、遠慮する必要はございません。
ご相談の場所を選ぶ際には、ぜひ「出張相談」をご検討下さい。
※葛飾区外への出張相談の場合、往復の交通費を頂戴する場合がございます。
料金のご案内
任意後見契約サービスの料金
| 任意後見契約サービス | |
|---|---|
| (参考)料金総額 |
10~20万円(前後)
《料金の内訳》 上記の料金には、以下のものが含まれております。 ・当事務所にお支払いいただく料金(税込8万8,000円) ・公証役場にお支払いいただく手数料◆ ・戸籍謄本等の取得手数料や交通費などの実費◆ ・予備受任者を引き受けていただく提携先専門家への謝礼(2万2,000円+交通費等の実費) ※当事務所代表に後見人を任せる場合のみ 《お断り》 |
| 着手金額 | 4万4,000円(上記の料金総額のうち、ご契約時にお支払いいただく額です) |
| サービス詳細 |
以下の内容がすべてセットになっています。 ・任意後見契約の文案作成、公証役場に提出する戸籍謄本等の取得、 公証人の先生との事前打ち合わせ ・見守り等を行う委任契約の文案作成、公証人の先生との事前打ち合わせ、契約締結 ※当事務所代表に後見人を任せる場合のみ ※必要により、公証人の先生にお客様ご指定の場所まで出張していただく手配も行います。 |
| こんな方におすすめ | ●認知症になった際、信頼できる人に財産管理、手続き・契約を任せたい方 |
| 備考 |
任意後見契約締結当日は原則として、公証役場までおいでいただきます。 お体の不自由な場合などは、お申し出下さい(出張手配をいたします)。 |
当事務所代表があなたの後見人を引き受ける場合のみ発生する料金
当事務所代表が後見人になる場合は、公証役場にて任意後見契約及び委任契約を締結後、
契約内容に基づき、お支払い事由が生じた場合に当事務所所定の料金をお支払いいただいております。
委任契約の料金
| お支払い事由 | 料金(税込) |
|---|---|
| 定期電話連絡 |
無料/1回あたり ※定期電話連絡は週1回を上限として行います。 なお、ご契約当初は月1回程度の頻度にてご連絡差し上げております。 |
| 定期面談 |
3,300円/1回あたり ※定期面談は月1回を上限として行います。 あなたのご自宅等への出張をご希望の場合、交通費を別途頂戴いたします。 |
| 入院手続き |
1万1,000円/1回あたり ※この他、治療費、薬代、差額ベッド代など、病院に支払うべき実費が発生いたします。 |
| 入院中のご自宅への立ち入り管理 | 550円/1日あたり |
| 各種契約をする場合のご同席 |
1万1,000円/1回あたり ※デイサービスの利用契約、不動産賃貸借契約などが対象です。 |
こちらに記載のないものにつきましては、文案打ち合わせ時にご案内いたします。
委任契約に基づく各種料金は、その都度ご請求いたします。
現金または銀行振り込みにてお支払いいただきます。
任意後見契約(後見人業務)の料金
| 管理財産総額 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 2万2,000円 |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 3万3,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 4万4,000円 |
| 1億円以上 | 5万5,000円 |
| 追加料金 |
2万2,000円/手続き1回あたり ※老人ホームの入居契約、要介護認定、入院手続きなどが対象です。 |
管理財産総額は、当事務所代表が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求する時点における、
あなたがご所有の財産(不動産の評価額、銀行預金の残高など)によって計算いたします。
(業務期間中の財産総額の増減により、上記の表の中で適用する料金を変更することがあります)
任意後見契約(後見人の業務をしたことに対する料金)は、毎月1回、定期的にお支払いいただきます。
ただし、追加料金に該当する業務(特別養護老人ホームへの入居契約など)を行った場合は、
追加料金をその都度ご請求いたします。
任意後見契約に基づき後見人の業務を当事務所代表が行う場合、
あなたの預金通帳などをお預かりすることになることから、
お支払いにつきましては、管理している預貯金から当事務所代表が引き出す形にて頂戴いたします。
家庭裁判所において選ばれる任意後見監督人への報酬も、毎月お支払いいただくこととなります。
任意後見監督人への報酬の額は、家庭裁判所が決めるため、上記の料金表には記載しておりません。ご了承下さい。
恐れ入りますが、お引き受け可能件数に制限がございます
当事務所では、
- 一人一人のお客様に寄り添い、的確なサポートをする
- 改葬手続きをできる限りスムーズ・スピーディーに進める
- これらにより、ご満足いただけるサービスを提供できるように努める
ことを大切にしております。
そのため、大変申し訳ございませんが、1か月あたりの任意後見契約サービスにおけるお引き受け可能件数を、
3件までに制限させていただいております。
また、当事務所代表に後見人を任せることをご希望の場合については、
当事務所代表が後見人の業務を承っているお客様の人数が一定数に達した場合、
当事務所が小さな事務所であるゆえ、お一人お一人にしっかりと寄り添ってご対応することが難しくなりますので、
ご相談・ご依頼の受付自体を一旦ストップいたします。
(※本日時点では、まだご対応可能です)
お早めにお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
任意後見契約サービスの流れ
1.お問い合わせ(ご連絡)
2.ご相談(お客様とのご面談) ※対面にて実施
併せて、任意後見契約締結の流れや当事務所のサービスについてご説明いたします。
なお、後見人をお任せする方について、
この時点でご同席なさるかどうかは任意です。
もしご同席される場合には、後見人の職務などの詳細について、
併せてご案内いたします。
【ご相談時にご用意をお願いするものについて】
以下のものをご用意下さい。
- ご自身が認知症になった際に後見人をお任せする方について、
①氏名
②住所
③生年月日
がわかるもの(メモ書き等で大丈夫です) - 認印
- 本人確認書類(運転免許証など)
これらをご用意いただけますと、スムーズに話ができます。
3.ご契約

当事務所のサービスについてご納得いただけましたら、ご契約となります。
その際、着手金をお支払いいただきます
(その場で現金払いまたは指定期限までに銀行振込)。
当事務所では、ご契約前のご相談の際に、サービス内容や料金をご説明し、
ご納得いただけてから契約することにしております。
強引に契約を進めることや、しつこく勧誘することはございませんので、どうぞご安心下さい。
4.作成のために必要な作業の実施

まずは当事務所にて、
・戸籍謄本等、公証役場に提出する書類の取得
・文案の作成
・(当事務所代表に後見人を任せる場合のみ)予備受任者の手配
これらが終わりましたら、ご連絡を差し上げます。
5.打ち合わせ
後見人を任せるお相手の方(当事務所代表を後見人とする場合は、予備受任者)を交え、
・文案の読み合わせ
を行います。
初回ご相談時にお相手の方がいらっしゃらなかった場合は、この段階で、お相手の方に、
当事務所代表から後見についての詳細をご案内いたします。
読み合わせた結果、内容に問題がなければ、
・公証人の先生との事前打ち合わせ、契約締結日の予約
6.公証役場(または公証人の先生の出張先)で契約締結
公証人の先生との打ち合わせの際に予約した日時に、
あなたとお相手の方に、公証役場においでいただき、任意後見契約を締結します。
(出張をご希望の場合は、あなたがご指定の場所に公証人の先生がいらっしゃいます)
当日は当事務所代表も同伴し、許可が得られれば同席いたします。
なお、以下の点にご留意下さい。
- 当日は実印を忘れずにお持ち下さい。
- 公証役場手数料は、作成時に窓口にてお支払いいただきます。
当事務所での立替払いはいたしません。
手数料額は事前にお伝えいたしますので、ご用意をお願いいたします。 - ご訪問いただく日時については、あなたとお相手の方のご希望に合わせて設定いたしますが、
公証役場の空き状況により、ご希望の日時が手配できない場合がございます。
そのため当事務所では、事前に第3希望までお伺いし、調整を行っております。 - 基本的に葛飾公証役場を利用しておりますが、他の公証役場での作成も可能です。
- ご契約から公証役場での作成までは概ね1か月程度です(状況により長くなる場合もございます)。
5.業務完了、料金精算

すべての手続きの終了後、料金を精算いたします。
料金総額から着手金を引いた残額を、現金または銀行振込でお支払いいただきます。
(銀行振込の場合は当事務所が定める期限までにお支払いとなります)
◆当事務所代表(行政書士 奥田航平)を後見人とする契約を締結した場合は、
以降は、まず「委任契約」により、定期的なご連絡と面談を実施して参ります。
【参考:実際に後見をするには】
任意後見契約に基づき、実際に後見を行うには、次の流れによることとなります。
- ①契約の相手方(任意後見受任者)が、あなたに認知症の症状が出ていないか確認
- ②認知症の症状が出ていると疑われるときは、家庭裁判所に提出する書類の様式を確保する
- ③任意後見受任者があなたを病院に連れて行き、診察・検査を受けさせ、
認知症によって判断能力が低下している旨の診断書(家庭裁判所の様式)を発行してもらう - ④戸籍謄本など、家庭裁判所に提出する書類を準備する
- ⑤書類が揃ったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
- ⑥家庭裁判所により、任意後見監督人が選任される
- ⑦これをもって後見が開始するので、任意後見受任者改め任意後見人が、
任意後見監督人のアドバイスを受け、任意後見契約の内容に基づいて財産管理などをしていく
(預金通帳を預かる、老人ホームへの入居手続きをするなど、必要に応じて実施)
この中で特に大事なのは①です。
なぜなら、任意後見契約は、認知症の症状が現れ、判断能力が失われつつある時に、
家庭裁判所に申し立てをすることで、適切なタイミングで始めることができるからです。
後見をスタートさせるのが遅すぎると、任意後見契約をした意味がなくなってしまいます。
状況を常に把握しておくことが大切となります。
参考になさって下さい。
よくあるご質問
Q1.任意後見契約には、向き不向きがありますか。
はい、ございます。
一般的に、任意後見契約は、認知症対策として主にご高齢の方にお勧めしているのですが、
特に、以下のいずれかに該当するようでしたら、ご利用を強くお勧めいたします。
- 後見人をお願いしたい特定の方(信頼できる方。ご親族、ご友人や専門家)がいる
- 障害のある子供の親が、子供の後見人となる
- 後見人をお願いできる親族がおらず、友人や専門家に任せたい
- 介護施設への入居手続きなど、各種手続き・契約をお願いできる人が身近にいない
- 認知症への法的な対策をするにあたり、初期費用を安く抑えたい
一方、上記に該当せず、以下のいずれかに該当するようでしたら、任意後見契約ではなく、
「家族信託」のご利用を検討することをお勧めします。
- 自分の財産の管理を、家族に「より柔軟な形で」任せたい
(株式投資、不動産の任意売却、賃貸用アパートの経営など) - 相続税対策も兼ねて、所有不動産の買い換えや賃貸用アパートの建て替えをしたい
- 家庭裁判所での手続き、第三者(任意後見監督人)の関与を避けたい
- 数世代にわたる財産の承継や、飼っているペットよりも先に死んでしまった場合の対策、
自分が死んだ後に残る障害のある子供の財産管理などに重きを置きたい - 認知症への法的対策をする場合にかかる「長期的な費用」を安く抑えたい
あなたの場合にはどのような形にするのが最適なのか、ご相談の中でご案内できますので、
まずは一度ご相談下さい。
Q2.既に認知症なのですが、任意後見契約を利用できますか。
軽度の認知症であれば、利用できる可能性があります。
任意後見契約は、公証役場で、公証人の先生によって契約書を作成し、公証人の先生の面前で締結します。
そのため、公証人の先生が、契約当事者に契約締結の意思と、判断能力が備わっていると判断すれば、
既に認知症であっても、利用できるというわけです。
なお、この場合、任意後見契約の締結後、直ちに家庭裁判所において任意後見監督人の選任を請求し、
後見人を引き受けた方が、後見人としての職務をスタートさせることになります。
任意後見契約の締結はできません。
この場合は、家庭裁判所において法定後見の申立てをすることになります。
Q3.任意後見契約をしても、認知症にならずに一生を終えたら、損になりませんか。
いいえ、損にはなりません。
確かに、任意後見契約を締結しても、認知症になることなく一生を終えた場合には、
あなたの死亡をもって任意後見契約は自動終了、ということになります。
この場合、任意後見契約の締結に係る費用負担が生じただけで、後見人をお願いした方にはその後の負担がありませんので、
損だ、という風に感じてしまうかも知れません。
ですが、任意後見契約は「保険」のようなものなのです。
例えば、火災保険。
火災保険は、保険期間内に火災などの事由が生じれば、保険金が支払われますが、
事由が生じなければ、原則、保険会社からあなたへの支払いは一切ありません。
それでも、保険料は定期的に支払っていますよね。
ですから、任意後見契約は、
「自分が認知症になったら、信頼できる人に助けてもらうための保険」と考えれば、
決して損だとは思わず、むしろ積極的に契約をする気になれるのではないでしょうか。
Q4.信頼できる人であっても、後見人をお願いできない場合はありますか。
お願いしたい方が以下に該当する場合には、お願いできません。
- 未成年者(満18歳未満)、破産宣告を受け復権を得ない者、行方不明者
- 家庭裁判所から法定代理人などを解任された経歴のある人
- あなたに対して裁判をしたことのある人、及びその配偶者と直系血族(子供など)
(あなたが訴えられた側、相手側が訴えた側。逆の場合も該当します) - 不正な行為、著しい不行跡などで任意後見人の任務に適しない人
- あなたの住んでいる場所から遠く離れたところに住んでおり、認知症になっていないか定期的に確認できない人
- 病気や障害などで、現実的に任意後見人の任務に耐えられない人
- 任意後見契約制度への理解が乏しく、任意後見監督人や家庭裁判所との関係が悪くなりそうな人
上4つは法律上「お願いできない人」として定められているもので、下3つは現実的に選ぶのが難しい人です。
また、上表にはありませんが、あなたよりも年上、またはあなたと同世代の方ですと、
お願いしたお相手自体が認知症、病気などで後見人としての仕事ができないリスクがあります。
ですので、あなたよりも年下(可能であれば親子くらい年が離れている)の方を選ぶのが理想的ではあります。
上記に当てはまるようでしたら、別の方を探していただく必要がありますので、ご留意下さい。
Q5.「預金の出入金」のみを職務とした任意後見契約もできますか。
制度上は、そのような形での契約もできます。
任意後見契約は、後見人となる方に何を任せるのか、オーダーメイドで決めることができます。
そのため、任せる内容を限定することも可能です。
ただ、質問のように「預金の出入金」のみを任せたい場合、銀行によっては、
「予約型代理人サービス」という、本人に代わって預金の出入金ができる人を登録しておくサービスがあります。
そのため、例えば、同居のご家族がいらっしゃって、ご自身の口座が認知症で凍結されるリスクだけが心配であれば、
わざわざ任意後見契約をせずとも、このサービスを利用し、
同居のご家族のうちのどなたかを代理人として登録してしまえば、それで足りてしまいます。
財産管理から各種手続き・契約まで、幅広く、信頼できる人に任せるという場合です。
当事務所では、あなたにとって最適な形が任意後見契約なのか、それとも他のものなのか、
お調べすることができますので、ぜひ一度ご相談下さい。
Q6.任意後見契約の締結後、相手との信頼関係が壊れた場合はどうすれば良いですか。
この場合、契約を解除することができます。
解除のしかたは、
- 相手方に、公証人の先生の認証文をつけた解除通告書を、内容証明郵便で送る
- 双方が顔を合わせて話し合える状況ならば、公証役場で契約解除の書類を作る
なお、契約解除のサポートも当事務所で行えます(有料)ので、いつでもご連絡下さい。
Q7.私は入院中ですが、任意後見契約サービスを利用できますか。
はい、条件付きではありますが、できます。
・意識不明など、任意後見契約締結ができない状態ではない
・会話や署名捺印が問題なくできる
公証人の先生には病院まで出張していただけますので、
公証役場に行くことなく、このサービスをご利用いただけます。
Q8.私は葛飾区民ではないのですが、対応してもらえますか。
契約の相手方が当事務所代表以外の方で、当事務所では契約締結のサポートを行う場合
はい、喜んで対応いたします。
どちらにお住まいであっても、ご対応可能です。
ぜひ、ご相談下さい。
当事務所代表を任意後見契約の相手方(任意後見受任者)としたい場合
基本的には、喜んでお引き受け申し上げます。
ただし一点、あなたが大阪に住んでいらっしゃるなど、当事務所から遠く離れている場所にお住まいの場合には、
お住まいの地域で任意後見契約に対応している専門家をご紹介の上、
当事務所代表は予備受任者としてあなたをサポートする、という形をご提案いたします。
理由としましては、任意後見契約に基づき、後見人として実際にあなたの財産管理などを行うにあたっては、
あなたのお住まいと当事務所が、近ければ近いほど、動きやすいという事情があるためです。
もちろん、当事務所代表(行政書士 奥田航平)をご指名いただけることはとてもありがたいですし、
信頼いただいた以上、どちらにお住まいであっても職務を全うするのは当然のこととしてお約束しております。
しかし、お住まいが遠方ですと、移動のための交通費が高くついてしまうところ、
業務により発生する実費はその全額をあなたの財産(預貯金)から頂戴するという形となるため、
お住まいの地域の専門家に依頼する場合と比較して、金銭面のご負担が大きくなってしまう懸念がございます。
あなたから頂戴する料金が過大になってしまうのは、制度の趣旨にそぐわないと考えます。
このことから、地元の専門家をご紹介する形を取ることがございます。
その点はご了承いただければ幸いです。
Q9.いつ、相談をすればよいのでしょうか。
認知症に備えたいなと考えるようになったら、すぐにご相談下さい。
なぜならば、任意後見契約を締結するにあたっては、あなたご自身が健康であることが必要なところ、
お年を召されると、どうしても、この先何十年にもわたって健康でいられるという保証はないためです。
資格者(当事務所代表)のご紹介

相続・遺言パートナー
相続専門行政書士 奥田 航平
(東京都行政書士会 登録 第13082587号)
1988年生まれ、東京都葛飾区出身、2014年開業。
終活や相続対策を頑張りたいすべての方のために、日々奮闘しております。
あなたからのご相談・ご依頼に直接対応いたします。
推薦者の声

|
行政書士 鈴木恵子先生 信頼できる行政書士です。 相続手続き、遺言書作成を専門とされている奥田先生は、 葛飾区を中心とした地域密着型で、 お客様の立場に立って、親身に相談に乗って頂ける先生です。 |
認知症への法的対策をして、この先の安心を得たいなら、まずご相談を

最後に、繰り返しになりますが、
もしあなたが、将来、認知症になってしまった場合の法的な備えをしたいとお考えなら、
ぜひ、当事務所ご相談下さい。
当事務所では、
- 任意後見契約の締結に向け、手続きを全面サポート
- 後見人をお願いする方にどんなことを任せるのがよいか、具体的にご提案
- 当事務所代表が後見人の役回りを承ることも可能
により、あなたの終活(認知症対策)を支えます。
もちろん、あなたの不安なお気持ちや疑問にもお答えします。
ですので、相談をするだけでも、これからの人生に前向きになれます。
お気軽にご相談下さい。
追伸:お客様にお伝えしたいこと

高齢者の数が増える中で、認知症の患者数も着実に増えつつあります。
また、脳卒中などの病気や、精神的な障害により、認知症でなくても、
判断能力が低下し、認知症の方と同じような状況に陥っている方も、多数いらっしゃいます。
そのような状況に備えるのが任意後見制度なのですが、
2000(平成12)年の制度発足以降、利用する方が着実に増えてはいるものの、
あまり有効活用されていないというか、積極的に利用しようとする方がまだまだ少ない、
という現状があります。
しかし、誰もが、認知症や病気などで、財産管理や契約などができなくなってしまうリスクを持っているのです。
ですから、もし、何もしていないまま、認知症や病気などで判断能力が低下してしまえば、
ご家族やご親戚の方に迷惑をかけてしまう結果にもなりかねないのです。
だからこそ、当事務所は、「終活・相続対策専門の事務所」として、
- 任意後見契約の締結をサポートすることで、あなたのみならずご家族などにも安心をご提供
し、万一認知症になっても、財産管理などで困らないようにします。
強くそう願っております。

当事務所に電話をかけることができます。
お電話での受付時間は、
平日…09:30~17:30
土日祝日…10:30~17:30 です。
ただし、受付時間が変更になる日や、
休業日(当事務所は不定休です)がございます。
こちらでご確認をお願いいたします。
なお、お電話でお問い合わせいただく場合、
急用、お客様対応等のため、営業時間内であっても、
留守番電話での対応となることがございます。
もし、留守番電話の音声が流れましたら、
お名前と電話番号を録音願います。
後ほど、折り返し、当事務所からご連絡を差し上げます。
また、当事務所の電話機の仕様上、
電話番号の録音がございませんと、
折り返しのご連絡ができなくなってしまいます。
お名前に加え、電話番号を必ずお知らせ願います。
付記:来所相談をご希望のお客様へ
JR金町駅からお越しの場合
北口を左折し、「理科大学通り」を直進。
イトーヨーカドー跡地の先にある信号つき交差点を左折し、2分ほど歩くと、
右手側に見える大きなマンション、「プラウドシティ金町ガーデン」に当事務所はございます。
「スポーツクラブルネサンスKSC金町24」手前の交差点に着いたら、その右手側に入口がございます。
JR金町駅北口から徒歩約7分です。
京成金町駅からお越しの場合
改札を出たら左折し、すぐにもう一度左折。末広商店街の道をまっすぐ進みます。
「金町湯」という銭湯の角にある交差点を右折。
常磐線の高架下(頭上注意)を抜け、直進し、横断歩道を渡ると入口がございます。
京成金町駅から徒歩約8分です。
自転車でのご来所をご希望の方へ
自転車でのご来所をご希望の場合、到着後、来客用駐輪場にご案内いたします。
お車でのご来所をご希望の方へ
お車でのご来所をご希望の場合、ご来所予定日2日前までにその旨をお伝え下さい。
当事務所が入るマンション内の来客用駐車場をご用意いたします。
注1:諸事情により、手配できかねる場合がございます。
その場合は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。
注2:ご来所時に駐車料金を頂戴いたします。
料金は、ご相談に要すると見込まれる時間に応じ、100円~300円です。
入館方法について
マンションへの入館方法につきましては、お問い合わせ時にお電話またはメールにてお伝えいたします。
現在、ご来所でのご相談をご希望の場合、都合により、
事務室以外の場所にお通ししております。
なお、恐れ入りますが、オープンスペースとなりますため、
周辺環境が気になるようでしたら、
出張相談をご希望いただければ幸いです。
(お客様のご自宅等、ご指定の場所にお伺いいたします)
任意後見契約(成年後見制度)に関するお役立ち情報集
任意後見契約(成年後見制度)に関する情報を随時追加しています。
知っていれば何かと役に立つことを載せています。
ぜひご覧下さい。
>>詳しくはこちらをクリック